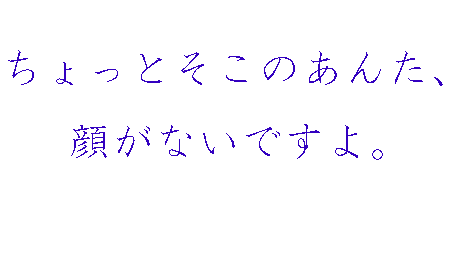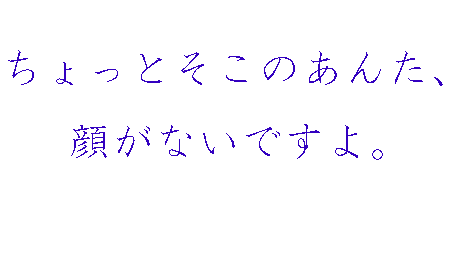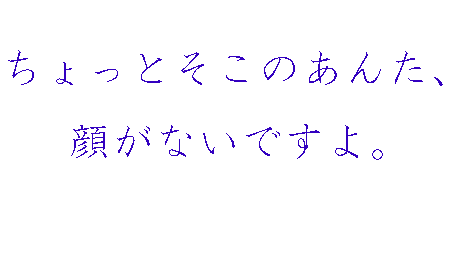 これは、写真家 藤原新也が1983年に出した写真詩集『メメント・モリ』を開くと、最初に出会うことばである。
これは、写真家 藤原新也が1983年に出した写真詩集『メメント・モリ』を開くと、最初に出会うことばである。
ウイスキーのCMポスターや、その頃は「社会派」というべき性格を具えて魅力的な写真週刊誌だった『フォーカス』に連載された氏のページから、興味を覚えて手にした本だ。
メメント・モリとは、「死を想え」というラテン語らしい。何もかもが「キレイ」に覆い隠された現代のニッポンという一面を浮き彫りにしてくれる。
氏は、生と死という生命の基本線から目をそらした今の我々のありさまを、あべこべ社会と評している。
よってたつべき地表が覆い隠されていたのでは、足元がおぼつかない。
近年、ミスターチルドレンが『花−メメント・モリ』という曲を出す際に、藤原新也のこの書物をラジオで紹介していたので記憶によみがえった。
過日、高崎山のお猿さんのボスが交代したというコラムを読んだ。
ボスのいたらないところを補い信望のあったナンバー2がボスの座を得るのに、さほどの困難もなかったという。
しかしボスになってからは、様子がちがうそうだ。病気の子供や傷ついた仲間をいたわることもしない。皆は次第にボスには寄り付かなくなったそうだ。そうなると、あとはボスの座を誇示するように威嚇を繰り返す。結果ますます仲間が離れていくという。
どうも他人事(サル事?)のように思えない。
特定の人物に批判的な姿勢で「自分ならこうする」という行動は、よくあることだ。
そのことで注目を集めることができても、基になる発想は批判している対象から出てきたものだけに独自性がない。「他人のフンドシで相撲をとる」ようなものだ。
対抗心やコンプレックスからの発想なのか、あるいは自分の内なる必要性からの発想なのかの見極めが必要なのかもしれない。
仮にコンプレックスからの発想であったとしても、自己の内なる欲求にまで掘り下げなければ「顔がない」ということなのだろう。
『メメント・モリ』 より
本当の死が見えないと、本当の生も生きられない。等身大の実物の生活をするためには、等身大の実物の生死を感じる意識をたかめなくてはならない。・・・・
長圓寺のホームページへ